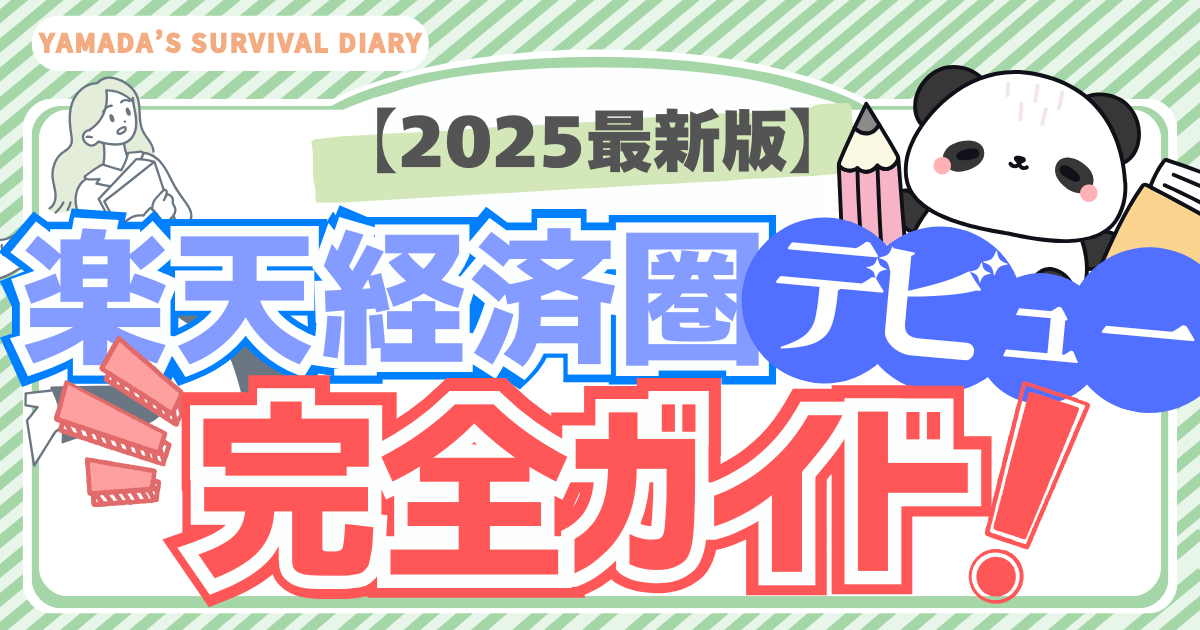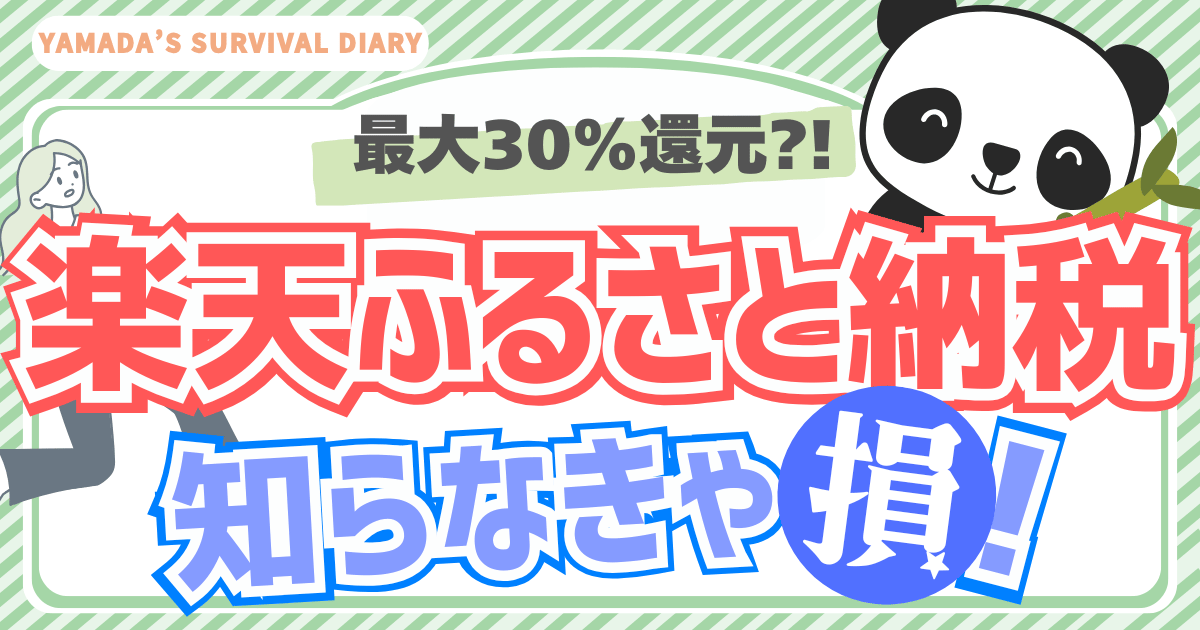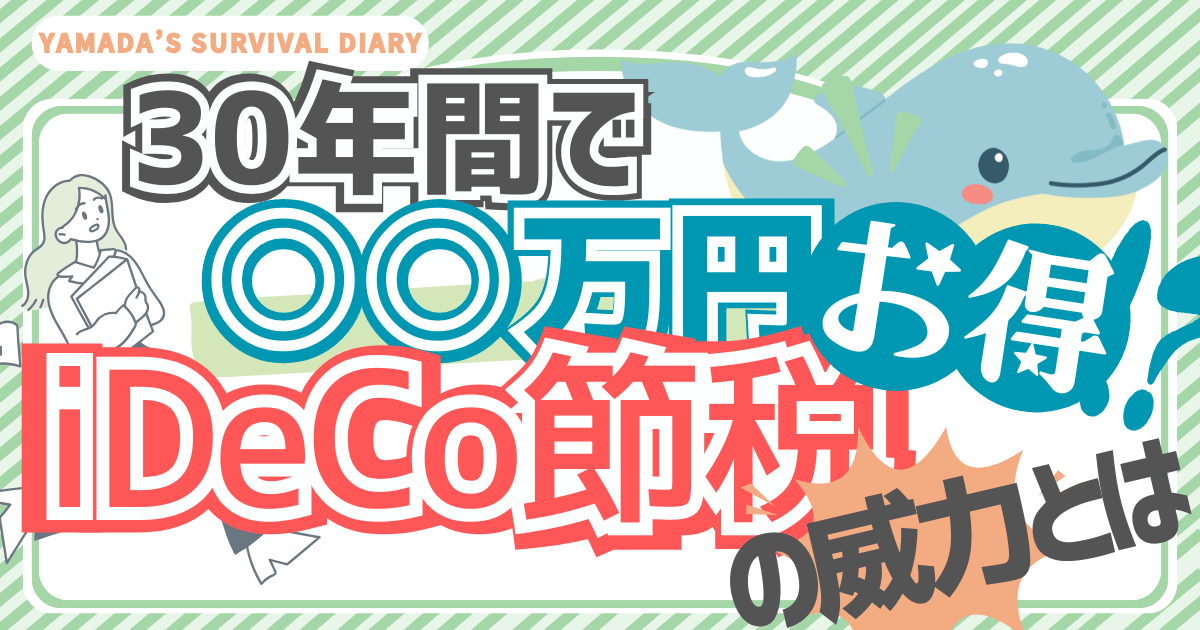- iDeCoを始めたいけど、「どれくらい節税になるのか」がイメージできない人
- 副業をしていて、節税との相性や影響が気になっている人
- 元本保証型と運用型、どちらがいいのか迷っている人
私は2023年からiDeCo(イデコ)へ満額積立を開始し、今年で3年目になります。
積立額は会社員なので月23,000円が上限です。
2025年7月現在ではおよそ31ヶ月投資を続け、合計713,000円投資したことになります。
「iDeCoは節税制度だと聞くけど、実際はどのくらいお得なの?」
「運用利回りはどれくらい?」
「元本割れはないの?」
そんなあなたの疑問を解決する内容となっています。
ぜひ、私のリアルな数字を参考にして資産形成に役立ててください。
【iDeCoの開設は、楽天証券がおすすめ! こちらのバナーから簡単に解説できます】
イデコって本当におトク?まずは基本の「節税効果」から

まずイデコとは? という疑問に対し、初心者にも分かりやすく解説していきます。
投資初心者にもわかりやすいイデコの3つの節税ポイント
イデコは一言で言うと、「個人で作る年金のこと」
国民年金や厚生年金保険は国や会社が行っていますが、イデコは将来に備えて自分で加入する年金です。
そんなイデコには、3つの節税メリットがあります。
- ①掛金が全額所得控除
-
例えば、年収650万円の人の場合、給与所得控除などを引いた額を約400万円として、
毎月2万円を投資信託で積み立てた場合、年間およそ7万2,000円の節税になります!
- ②運用益も非課税で再投資できる!
-
通常なら投資は、その運用益に約20%の税金がかかります。
しかし、イデコなら運用益が全額収益となり再投資することができます。
引き出す時まで運用益を再投資し続けるので、複利の効果を十分活かすことができます。
- ③受け取る時も大きな控除!
-
イデコは退職金と同じ、退職所得控除を利用することができます。
一時金で受け取る場合は、勤続年数20年(イデコ加入期間)以上の場合、退職金と合わせて2,340万円までは税金がかかりません!
但し、イデコは出口が複雑!
一時金で受け取るのか、毎年まとまった額を受け取るのかでこの控除が使えない場合もあります。また、先述したように控除額には上限があるため、一番お得にお金を受け取れる方法を学んでおく必要があります。
しかし、出口が複雑であることを差し引いても、所得控除や運用益の非課税制度など、お得となるメリットの方が大きいです。
所得控除は「課税所得」を減らす仕組みで、課税所得とは年収から各種控除(基礎控除や保険料控除など)を引いた金額のことです。
所得控除のしくみ|節税になる理由をカンタンに解説
先述した、「①掛金が全額所得控除」についてさらに詳しく解説します。
イデコは掛金の全額が所得控除となります。この所得控除から得られる節税額は以下の3スッテプで計算できます。
会社員の場合、月額上限は 23,000円(最大)
→ 年間:23,000円 × 12ヶ月 = 276,000円
所得税:課税所得に応じて5%〜45%(年収400万円の場合10%、年収500万円の場合20%))
住民税:全国一律約10%
👉 計算式:節税額(年間)=掛金 ×(所得税率+住民税率)
この1~3のステップで、実際に計算してみましょう。
具体例として、年収400万円、独身、会社員の場合、
| 課税所得 | ざっくり約270万円前後 |
| 所得税率 | 10% |
| 住民税率 | 10% |
| 年間掛金 | 276,000円(23,000円 × 12ヶ月) |
| 節税額 | 276,000円 ×(10%+10%)= 55,200円 |
年収400万円、独身、会社員の場合、年間55,200円の節税になります。
浮いたお金を生活費に回すのも良し。NISAの掛金にして1,800万円の枠をいち早く埋めるのも良し。趣味に充てて人生のQOLを上げるのも良し。
お金があればそれだけ選択肢が広がりますね。私の使い方については後述します。
副業女子の私が実際に「いくら得しているか」計算してみた
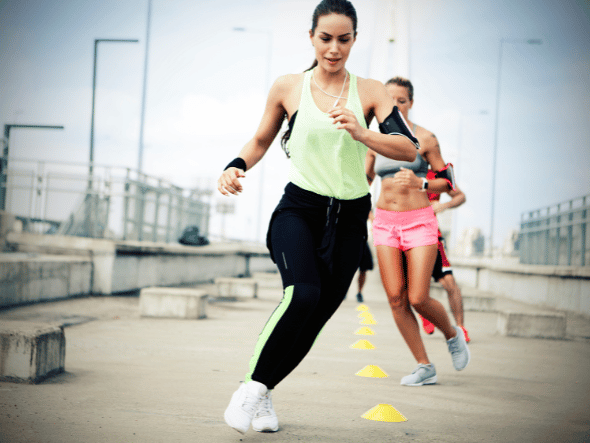
実際に私がいくら得しているのか計算してみました。
独身か扶養家族がいるのか。年収。掛金額によって変わってきますが、おおよその目安になると思います。ぜひ参考にしてみてください。
私の掛金・年収・節税額をリアル公開!
私の掛金、年収、家族構成については以下の通りです。
| 掛金 | 276,000円/年(23,000円×12ヶ月) |
| 年収 | 580万円 |
| 家族構成 | 独身・一人暮らし |
年収から、所得税10%、住民税10%となります。
なので節税額は、
276,000円×(10%+10%)= 55,200円/年
年間およそ55,200円の節税です!
シミュレーション結果|5年後・10年後の節税効果は?
1年後、5年後、10年後、20年度の節税効果は以下の表の通りになります。
| 年数 | 節税額累計 |
| 1年 | 55,200円 |
| 5年 | 276,000円 |
| 10年 | 552,000円 |
| 20年 | 1,104,000円 |
10年以上イデコを継続していたらおよそ50万円、20年以上では100万円の節税!
イデコの掛金は全額、課税所得から控除されるため、所得税と住民税の両方で節税効果があります。
この「浮いた5万円」をNISAで運用した場合、5万円以上の価値が生まれるのです!
課税所得別「iDeCoの節税額」ざっくり早見表

イデコの節税額は、あなたの生活環境と年収によって変わってきます。
年収別、扶養あり・なしで計算してみました。
年収300万/400万/500万…実際どれくらいトクする?
年収別のざっくりとした節税額を表にまとめました。
計算方法の詳細は前述の通りです。
また、条件として独身、会社員で、毎月23,000円の最大掛金の場合で計算しています。
| 年収 | 課税所得 | 所得税率 | 節税額の目安(年間) |
| 300万円 | 約102万 | 5% | 約41,400円 |
| 400万円 | 約150万 | 5% | 約41,400円 |
| 500万円 | 約220万 | 10% | 約55,200円 |
| 600万円 | 約282万 | 10% | 約55,200円 |
| 700万円 | 約353万 | 20% | 約82,800円 |
年収が上がるほど節税額が増え、その分節税メリットが高くなります。
ポイントとしては、
- 控除対象は「課税所得」なので、扶養や保険料控除があると減る
- 年末調整でiDeCo分を申告すればOK(企業型でない限り確定申告不要)
- 節税額が増える=その分キャッシュでおトクになる!
扶養があると控除額はどう変わる?
扶養家族がいた場合、一人につき扶養者控除38万円が控除額に加わり、課税所得が低くなります。
簡単に扶養家族の人数とイデコの節税額について表にまとめました。
| 条件 | 控除内容(概算) | 課税所得 | 所得税率 | iDeCo節税額 |
| 🔹扶養なし(独身) | 基礎控除48万+社保87万=135万 | 406万 − 135万 ≒ 271万 | 10% | 55,200円 |
| 🔸配偶者扶養あり | 上記+配偶者控除38万=173万 | 406万 − 173万 ≒ 233万 | 10% | 55,200円 |
| 🔸配偶者+子1人扶養あり | 上記+扶養控除38万=211万 | 406万 − 211万 ≒ 195万 | 5% | 41,400円 |
あくまでざっくりとした計算ですが、年収によっては独身と扶養家族1人の節税額は変わりません。しかし、配偶者と合わせ子供1人の扶養が増えた場合、課税所得が195万円以下となり所得税が5%になってイデコの節税額も低くなります。
また、子供の年齢によっても変わってくるので注意です。
なので、シミュレーションサイトなどを活用し、自分にとってどれくらいお得になるのか計算することが大切です!
個人的にはろうきんが提供しているシミュレーションが条件を詳細に入れることができ、運用利回りなども確認できて便利でした。
こちらのサイトからご活用ください
副業の有無でどう変わる?所得が増えると節税も増える!
また、副業収入の有無によっても節税額が変わってきます。
こちらも表にまとめてみました。
| 副業収入(年) | 課税所得 | 所得税率 | 節税率(所得税+住民税) | iDeCo節税額(年) |
| 0円 | 2,710,000円 | 10% | 20% | 55,200円 |
| 120,000円 | 2,830,000円 | 10% | 20% | 55,200円 |
| 240,000円 | 2,950,000円 | 10% | 20% | 55,200円 |
| 360,000円 | 3,070,000円 | 10% | 20% | 55,200円 |
| 600,000円 | 3,310,000円 | 20% | 30% | 82,800円 |
| 1,200,000円 | 3,910,000円 | 20% | 30% | 82,800円 |
ポイントは、私のような本業収入580万円の場合、副業収入が60万円を超えると課税所得が330万円を上回り所得税率が10%から20%へアップします。
これにより、節税額も55,200円から82,800円へ大幅アップ!
副業で稼ぐ金額によって変わってくることを覚えておきましょう。
控除で浮いたお金、どう使う?投資・浪費・自己投資の考え方

ここからは、控除によって浮いたお金の使い道について解説していきます。
あなたにあった使い方をぜひ、見つけてください。
「浮いたお金で〇〇を買った」使い道もリアルに紹介
私は浮いたお金は全額新NISAの成長投資枠でS&P500に連動している、「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」を購入しています。
例えば、イデコで節税できた55,200円をS&P500に連動するインデックスファンドに毎年積み立て、運用利回り7%と仮定した場合、
およそ5,579,232円(約557万円)になります!
シミュレーションの条件は表の通りです。
| 毎年の積立額 | 55,200円(iDeCoで節税した分) |
| 運用利回り | 年7%(S&P500の過去平均リターン想定) |
| 積立期間 | 30年間(30歳〜60歳) |
| 運用方法 | 年1回積立+複利運用 |
また、イデコで浮いたお金をただ貯金に回した場合と比較すると、
| 項目 | 金額 |
| 貯金だけの場合(運用なし) | 1,656,000円 |
| S&P500で運用した場合 | 5,579,232円 |
| 差額(=運用益) | 3,923,232円 ✅ |
同じ金額を「運用するか/しないか」だけで、最終資産は約3.9倍の差!
この節税+再投資の威力は、未来への大きな資産作りに直結します。
自己投資 or 再投資、どっちが正解?バランスのヒント
もちろん、浮いたお金を自己投資へ回し、副業収入で大きく利益を得たり、本業で出世したりして収益を得ても◎
また、投資ではなく浪費に使い、生活の豊かさを上げるのもいいのではないでしょうか。
投資、浪費、どちらかが正解という訳ではありません。
あなたの人生が豊かになると思えるものに使ってください。
イデコの商品選びのヒント

イデコの商品には、リターンを狙う投資信託や逆に元本確保商品と呼ばれる定期預金や保険商品があります。
長期で積立できるのなら断然「投資信託」をおすすめします。
私は楽天でイデコを行っているため、毎月23,000円を「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」に積み立てています。
投資信託のため元本割れの危険性もありますが、過去のデータからインデックスファンドは、15年以上長期積立前提ならば元本割れせず、平均5〜7%の運用利回りを得られるという報告があります。
最終的にいくらお得なの?
①イデコをやらなかった場合、②イデコを元本保証型商品にした場合、③イデコをS&P500で運用した場合、④イデコの掛金も節税額もS&P500で運用した場合の最終資産を計算してみました。
条件は先述と同じ、30歳〜60歳の30年間で、年収580万円、独身(扶養家族なし)で計算しています。
| ケース | 積立元本(掛金)(A) | 節税額(30年合計)(B) | 最終資産(A+B) |
| ① iDeCoをやらなかった | 0円 | 0円 | o円 |
| ②元本保証型(利回り0%) | 8,280,000円 (276,000円×30年) | 1,656,000円 (55,200円×30年) | 9,936,000円 |
| ③S&P500で運用(利回り7%) | 8,280,000円を利回り7%で運用▶︎27,049,492円 | 1,656,000円 (55,200円×30年) | 28,705,492円 |
| ④ 掛金+節税額もS&P500で運用 | 8,280,000円を利回り7%で運用▶︎27,049,492円 | 1,656,000円を利回り7%で運用▶︎5,579,232円 | 32,628,724円 |
イデコをやらなかった場合は、当然節税額も資産額も0円です。
しかし、イデコ(276,000円/年)+節税(55,200円/年)を全てS&P500で運用した場合、なんと3,262万円も得ることができます!
これは、やる、やらないで差がつくレベル以上の成果です。
ただし、これはあくまでシミュレーションであって、結果ではありません。投資にはリスクがあります。自分にあったリスク強要度の商品を選ぶようにしてください。
まとめ|iDeCoは続けるほど「実感するおトクさ」がある
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
毎月の拠出金額はNISAに比べると少ないですが、イデコはNISAにはない節税制度が大きなメリットです。
最初こそ、小さな金額でも積み重ねて運用することで大きなリターンとなります。
自分に使える制度は大いに利用し、「やってて良かった」と思える未来の自分のために、ぜひイデコを活用してみてください。
この記事を読んだ人はこちらの記事もおすすめです